「ほらふき山の魔理沙」は本当に面白いのか? 体験版やレビュー評価を見ても、いまいちピンとこない方も多いのではないでしょうか? 本記事では、東方Project公認のテーブルトップ風RPG「ほらふき山の魔理沙」について、良い点・悪い点を徹底分析し、神ゲーかクソゲーかをズバリ予想します。 攻略・DLC・選択肢・マルチエンディングなどの注目キーワードも網羅し、プレイヤー目線でわかりやすく解説。 購入を迷っている方はぜひ最後までお読みください。

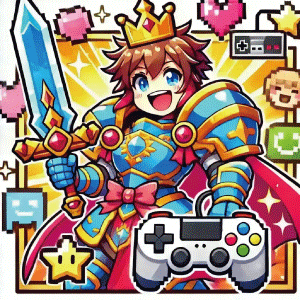
ほらふき山の魔理沙とは
「ほらふき山の魔理沙」は、東方Project公認の二次創作RPGであり、アライアンス・アーツが手がけた新感覚のテーブルトップ風アドベンチャーゲームです。 プレイヤーは博麗霊夢となり、突如として姿を消した霧雨魔理沙を探して、不思議な「本の世界」を冒険します。 この作品は、サイコロによる行動判定や選択肢によって物語が分岐する「ゲームブック」的要素を持ち、システムとしてはTRPGとビジュアルノベルが融合したような独特のスタイルを採用しています。
舞台となる「ほらふき山」や紅魔館など、シリーズおなじみのキャラや世界観がコミカルかつドラマチックに描かれており、東方ファンでなくとも楽しめるライトな雰囲気が特徴です。 プレイヤーの選択によって進行ルートやエンディングが変わるマルチエンディング仕様もあり、何度も遊べるリプレイ性の高い構成となっています。
ゲームジャンルとしての特徴
「ほらふき山の魔理沙」の大きな特徴は以下の通りです:
- テーブルトップスタイル:ボードゲーム風の演出と進行方式
- サイコロと選択肢による進行:運と判断力のバランスが求められる
- マルチエンディング搭載:周回することで新しい発見やルートが楽しめる
- 会話にツッコミが入る「実況風演出」:紅魔館キャラによるメタ発言が秀逸
- ストーリー重視:東方世界に忠実ながら、独自ストーリーが魅力的に展開
ゲームブックにTRPG的な遊び心を融合し、ファンだけでなくゲーム好きにも刺さる一本と言えるでしょう。
ほらふき山の魔理沙の発売日・定価・対応機種・ジャンル・メーカー
「ほらふき山の魔理沙」は、2025年9月19日に発売予定の東方Project公認RPGです。 対応プラットフォームはNintendo SwitchおよびPC(Steam)で、家庭用とPC両方に対応していることで幅広いプレイヤー層にアプローチ可能</strongとなっています。
ジャンルは「テーブルトップ風アドベンチャーRPG」で、サイコロを使った判定や、ゲームブックのような分岐と選択肢によって物語が進行します。 このようなスタイルは東方ゲームの中でも珍しく、従来の弾幕シューティングとは一線を画しています。
開発・販売は「アライアンス・アーツ」が担当し、過去には『幻想人形演舞』シリーズなど、東方二次創作の良質なタイトルを世に送り出している実績があります。
製品情報一覧(公式情報より)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイトル | ほらふき山の魔理沙 |
| 発売日 | 2025年9月19日(予定) |
| 定価 | 通常価格3,000~4,000円程度 |
| 対応機種 | Nintendo Switch / PC(Steam) |
| ジャンル | テーブルトップ風アドベンチャーRPG |
| メーカー | アライアンス・アーツ |
| プレイ人数 | 1人 |
Steam版ではすでに体験版が配信中で、ゲームの雰囲気や進行システムを事前に体験することができます。 気になる方はまず体験版をプレイしてみるのもおすすめです。
ほらふき山の魔理沙の良い点
「ほらふき山の魔理沙」は、二次創作ながら完成度が高く、ゲームデザイン・ストーリー・演出の面で非常に高評価を受けています。 以下にその魅力を詳しく分析していきます。
テーブルトップRPGの魅力と演出
本作最大の特徴は、ボードゲームやTRPGを彷彿とさせる「テーブルトップ演出」です。 物語の進行はサイコロ判定によって左右され、イベントの成功・失敗や戦闘の結果までもが運に委ねられます。
このサイコロ演出がプレイヤーに緊張感と偶然性によるドラマを与え、毎回違う展開が楽しめる「遊びごたえのある構造」となっています。 運が悪くて進行が失敗しても、それが物語の味わいになってくる絶妙なバランス設計です。
さらに、盤面風のマップ移動や、場面転換時の紙芝居風カットイン演出も見事で、まるで本当に「卓上RPG」を遊んでいるかのような没入感を与えてくれます。
キャラクターとストーリーの魅力
キャラクターの個性が非常に立っており、会話のテンポや掛け合いがユニークかつ軽快です。 紅魔館メンバーによる「ツッコミ実況」や、霊夢・魔理沙のちょっとズレたやり取りが、ストーリーをコメディチックに盛り上げます。
一方で、魔理沙の失踪というシリアスな主軸もあり、物語の奥深さが感じられる点も高評価。 ギャグとシリアスがバランス良く共存しており、テンションにメリハリがあって飽きずにプレイできます。
ゲームブック風の自由な選択肢
選択肢によって展開が大きく変わる「ゲームブック形式」も、非常に良くできています。 どのルートに進むか、どんな行動をとるかによって、出会うキャラクターや結末が変化します。
たとえば:
- 魔理沙をすぐに追う → 敵と直接対決、戦闘多めルート
- 情報収集を優先 → イベント多めで伏線を知れるストーリールート
- 寄り道して遊ぶ → 隠しキャラやBGMイベントが楽しめる寄り道ルート
このように、プレイヤーの選択が世界を大きく変える感覚は、まさに「自分だけの物語を紡ぐ」楽しさがあります。
周回プレイにも耐えうる内容と構造で、長く楽しめる設計となっている点は非常に優れています。
ほらふき山の魔理沙の悪い点
「ほらふき山の魔理沙」は高評価な点が多い一方で、気になる短所も存在します。 プレイヤーによってはゲーム体験を損ねる可能性もあるため、事前に把握しておくことが重要です。
サイコロ運の偏りがストレスになる
このゲームはサイコロ判定に大きく依存しており、特定のシーンで「運ゲー感」が強まることがあります。 たとえば:
- 重要なイベントシーンでの連続失敗
- 戦闘中の判定がすべてミスに終わる
- 低確率の行動に頼らざるを得ない展開
何度もリトライが必要な場合や、理不尽な展開が続くと、プレイヤーのモチベーションが下がってしまうことも。 リセマラやセーブ&ロードによってある程度のリカバリーは可能ですが、演出テンポの関係でやや煩雑に感じる面もあります。
ゲーム全体のボリューム不足
体験版およびプレリリース情報を見る限り、本作は比較的「コンパクトな内容」にまとまっている印象があります。
エンディングまでの到達時間は個人差があるものの、おおよそ4〜6時間程度と短めで、1周目を終えた段階で「もう少し遊びたかった」と感じる声も少なくありません。
ただし、周回要素や分岐ルートの存在により、ボリューム不足を補う設計にはなっています。 しかしながら、「一周の密度」を重視するプレイヤーにとっては、物足りなさを覚える可能性があります。
テンポや演出の冗長さ
演出面において、「テーブルトップ風」の雰囲気を重視するあまり、シーン展開のテンポがやや遅い部分があります。 たとえば:
- マップ移動演出が毎回挿入されてテンポが悪化
- サイコロの判定演出がスキップできない
- キャラの会話が冗長に感じるパートがある
特に周回プレイ時にはテンポの悪さが気になるプレイヤーが多く、スキップ機能の充実が今後の課題とも言えるでしょう。
これらの短所は決定的な欠点ではないものの、プレイスタイルや好みによっては評価を左右する要因となります。
ほらふき山の魔理沙は神ゲーかクソゲーか?(結論)
「ほらふき山の魔理沙」は、明らかに「神ゲー寄り」の作品です。 特に東方ファンや、ゲームブック・TRPG風のシステムが好きなプレイヤーには刺さる構成で、完成度の高い二次創作として高評価を得ています。
ただし、サイコロ依存の運要素やテンポの遅さ、一周ごとのボリューム感にやや難を感じるユーザーも一定数おり、万人向けというよりは「ハマる人には深くハマるタイプ」の作品と言えます。
以下は各パラメーターごとの採点評価です。
5つの評価パラメーターと総合得点
| 評価項目 | 点数(20点満点) | 評価内容 |
|---|---|---|
| ゲームシステム | 18点 | サイコロと選択肢による独自システムが新鮮。完成度も高い。 |
| ストーリー・演出 | 17点 | 東方世界を活かした設定と、笑いとシリアスのバランスが魅力。 |
| キャラクター性 | 19点 | 紅魔館メンバーの掛け合いと実況演出が秀逸。ファン満足度◎ |
| リプレイ性 | 16点 | マルチエンディングで何周も楽しめるが、テンポの悪さがやや足を引っ張る。 |
| コスパ・ボリューム | 15点 | やや短めだが、価格次第で十分満足できる内容。 |
| 総合得点 | 85点/100点 | 東方ファンには間違いなくおすすめ。RPG好きも要チェック! |
「ほらふき山の魔理沙」は、価格と内容のバランスを考慮すれば、十分に「神ゲー」と呼べるクオリティを持ったタイトルです。
プレイスタイルや好みによっては評価が割れるかもしれませんが、独自性と完成度の高さを考慮すれば、東方ファンでなくとも一度は体験してみる価値があると言えるでしょう。

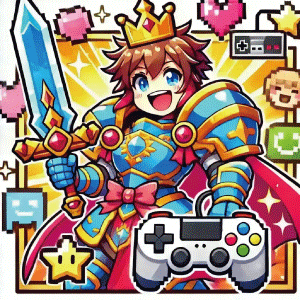





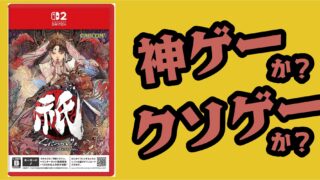


は神ゲーか?クソゲーか?感想・レビュー【PC・PS5・XSX】-320x180.jpg)
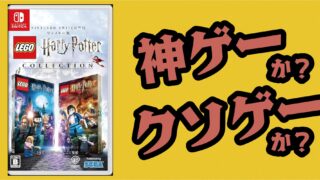








は神ゲーか?クソゲーか?感想・レビュー・評価【PS5・PS4・Switch・PC】-320x180.jpg)




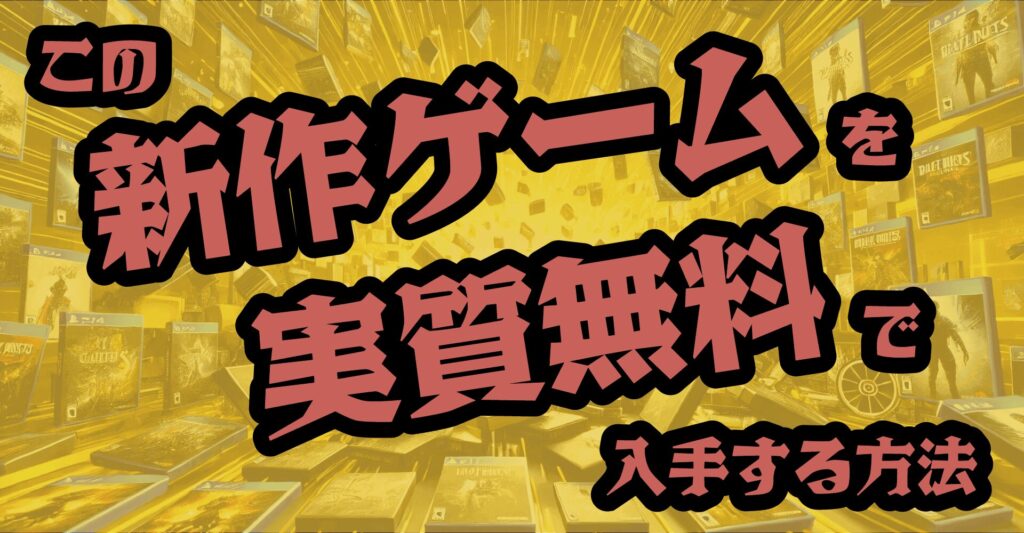
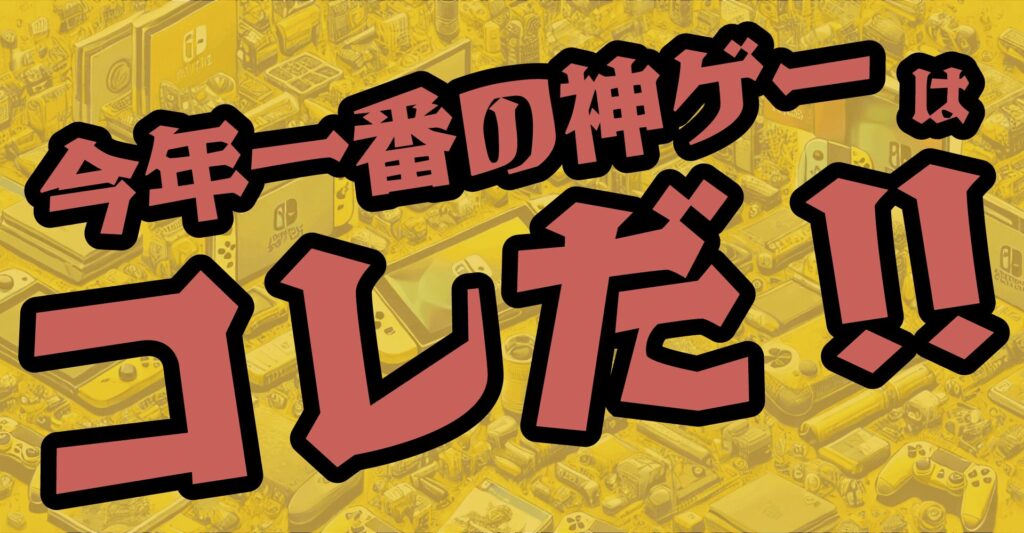


コメント